京文化と都会的な町並みが溶け合う烏丸御池エリア|この街の住みやすさは?
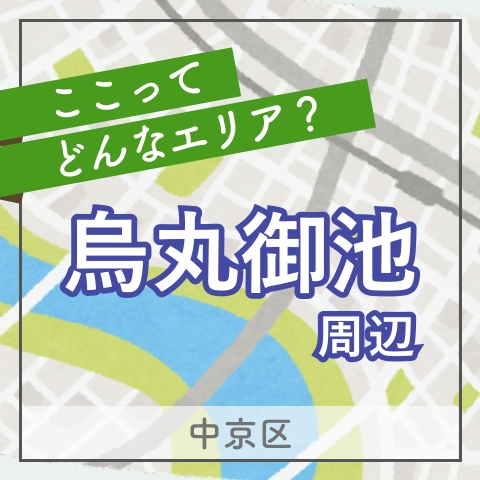
こんにちは。京都の魅力を伝えるライター・まる きょうこです。
この連載コラムでは、京都市内で土地探しをしている方へ向けて、私が歩いて見つけた京都の各エリアにまつわる歴史や楽しみ方を詳しくお届けしています。
今回ご紹介するのは、京都市の中心部にある烏丸御池エリアです。
[ 目次 ]
烏丸御池エリアについて
京都市営地下鉄の烏丸御池駅を中心とした烏丸御池エリアは、中京区に位置し、京都市のほぼ中央にあります。

烏丸御池駅は地下鉄東西線と烏丸線が接続するため、乗り継ぎ駅としても多くの人が利用しています。

このエリアに昔から住む方にお話を伺ったところ、
- お買い物は四条の大丸
- 大みそかは祇園の老舗蕎麦店「松葉」でにしんそば
- 年明けには京都ゑびす神社で行われるえべっさん
…と、ワクワクするような京都らしい暮らしぶりを教えてくれました。
7月には祇園祭の山鉾が巡行するエリアでもあり、とくに後祭では烏丸御池周辺に建つ山鉾も多く、周辺には山鉾の保存会が点在しています。
このような伝統的な京都の文化を残しつつ、新しいビルやマンションが建ち並ぶのも烏丸御池の特徴です。とくに御池通周辺は、都会的で洗練された雰囲気が漂います。

広々とした道路に街路樹が並び、どこか外国の都市部のような印象もありますね。河原町や祇園など、京都きっての繁華街も近く、利便性に魅かれて住む人も多いエリアです。
京都の中心を示すお寺「頂法寺(六角堂)」

烏丸御池駅の近くには、この辺りが京都の中心であることを示すお寺が存在します。六角形のお堂があることから六角堂の名で親しまれる頂法寺です。
聖徳太子が創建し、遣隋使で有名な小野妹子が住職を務めた歴史あるお寺で、境内には京都の中心を示すとされる「へそ石」が存在します。

頂法寺のお堂は平安遷都以前、現在よりもう少し南にあったとされています。お堂のある場所に道を作りたいと天皇が願ったところ、一晩のうちにお堂自ら移動してくれたのだとか。へそ石は、そのときのお堂の礎石だったといわれています。
頂法寺は、地元の人たちにも親しまれているお寺で、通勤やお買い物のついでに参拝する人の姿をよく見かけます。この地域で暮らす際には、ぜひお参りしていただきたいお寺です。
烏丸御池エリアで覚えたい「京都の通り名」

京都には、中国にならい取り入れた都市区画「条坊制」によって作られた、東西と南北に交差する道が残り、それぞれに「通り名」が付けられています。「まるたけえびすにおしおいけ…♪」という通り名の歌を聞いたことがある方もいるのではないでしょうか。
とくに烏丸御池エリアの「碁盤の目」と呼ばれる町並みは、京都ならではの風景です。
住所も町名とは別に、通り名に「上る・下る・東入る・西入る」と付けて表記することがあります。通り名さえ覚えていれば、とても合理的でわかりやすい表記の仕方です。

それぞれの通り名の由来を知ると、このエリアの魅力をより深く知ることができますよ。ここではそのいくつかをご紹介しましょう。
【御池通と烏丸通】駅名の由来となった二つの道

烏丸通と御池通が交差する場所にある烏丸御池駅。他地域の人にとってはなかなか珍しい駅名で、「からすまおいけ」と読めないことも多いとか。
御池通は、二条城近くの「神泉苑」にゆかりのある通り名です。

神泉苑は元々皇室の苑地で、かつては広大な土地を持っていました。苑内には龍神が住むといわれる大きな池があり、そこへ通じる道として御池通と呼ばれるようになったそうです。
一方、烏丸通の前身は「烏丸小路(からすまこうじ)」と呼ばれた平安京の道。通り沿いに烏丸という公家の邸宅があったとか、カラスの多い地域だったとか、名前の由来には諸説あるそうですよ。
【衣棚通】衣服を売っていた三条衣棚

衣棚通(ころものたなどおり)は、烏丸通の西側にある南北の道です。衣棚通と三条通が交わるところには、「三条衣棚の歴史」という説明板が立っています。
平安京には存在しなかった衣棚通は、豊臣秀吉の政策によって設置されました。周辺で呉服や僧侶の法衣を棚売りしていたことから、この通り名がついたのだそうです。
【釜座通】梵鐘や茶釜の鋳物師がいたエリア

釜座通(かまんざどおり)も烏丸通の西側を南北に通っている道です。かつてこの付近には、梵鐘(ぼんしょう)や茶釜を造る鋳物師が集まる「三条釜座」という組合がありました。
もっとも古くから鋳造をしていた大西家が現在も続いており、「大西清右衛門美術館」では歴代の茶の湯釜などが展示され、当時の様子を知ることができます。
【夷川通】かつて川が流れていた家具の街

夷川通(えびすがわどおり)は東西の通りの一つで、御池通の北側に位置しています。現在の夷川児童公園の北側あたりに流れていたとされる川が、通り名の由来とのこと。また夷川通には新旧のインテリアショップが軒を連ね、「家具の街」とも呼ばれています。。

烏丸御池周辺に住宅を建てる際には、ぜひ夷川通でお気に入りの家具を見つけてくださいね。
烏丸御池エリアに並ぶ町家と洋風建築

烏丸御池周辺には、京都らしい町家の風景と、明治以降に建てられた近代の洋風建築が混在しています。内部を見学できる建物もあるので、建築巡りをして住まいづくりのヒントを見つけてはいかがでしょうか。
三条通は洋風建築の宝庫
三条通は明治期の京都におけるメインストリート。
とくに寺町通から新町通に挟まれた三条通沿いには近代の名建築が集まり、「三条通界わい景観整備地区」として保存されています。
そのなかでも代表的な建物をいくつかをご紹介しましょう。
まずは、京都の歴史と文化を展示している「京都文化博物館」。

明治39年に建てられた旧日本銀行京都支店の建物で、国の重要文化財に指定されています。
設計は、東京駅をはじめ多くの近代建築を手がけた辰野金吾氏。赤レンガに白い花崗岩のラインを配置した外観は、「辰野式」と呼ばれる特徴的なデザインです。
展覧会が開催される本館の横に、銀行の営業室として使われていた別館があり、無料で見学できます。

クラシカルな装飾と吹き抜けの広々とした空間は、まるで舞踏会のホールのようです。
また別館と本館の間にある旧金庫室は、当時の面影を残したままカフェを営業しているので、ぜひそちらにも立ち寄ってみてください。
東洞院通を挟んで京都文化博物館と並んでいるのが、京都の登録有形文化財である「中京郵便局」。

中京郵便局は、日本で初めて「ファサード保存」が行われた建物として知られています。
ファサード保存とは、歴史的な建築物などの外観を残して、内部のみ新しく建て替える手法のこと。
一時は取り壊しが決定されていましたが、明治期の貴重な建物の保存を求める声が大きく、外観を残しつつ機能性も確保できるよう試行錯誤を重ねた末、現在の姿になったのだそうです。
烏丸御池エリアでランドマーク的存在として人気の「新風館」も、京都市の登録有形文化財です。

新風館の前身は「旧京都中央電話局」で、機能性や合理性を重視したモダニズム建築が特徴です。
2001年からは商業施設として活用されており、2020年の本格的なリニューアルでホテルや映画館を併設し、現在の姿になりました。
レトロな外観はそのままに、4つの庭を配置した館内は緑いっぱいの心地よいスペース。ランチやお買い物だけでなく、ほっとくつろげる場所として地域の人々に愛されています。
京都の暮らしに寄り添う京町家
京町家は、間口が狭くて奥行きのある「鰻の寝床」と呼ばれる構造が特徴です。
また、職住一体の暮らしを基本とし、社交的な空間とプライベートな空間とが機能的に分離されています。
そんな京町家の味わい深い暮らしを感じられるスポットをご紹介しましょう。
烏丸御池エリアで見学が可能な町家が、「八竹庵(旧川崎家住宅)」です。

八竹庵は、大正時代の豪商が建てた住居兼商談の場で、京都市の有形文化財に指定されています。
和洋折衷の町家建築で、関西建築界の父と呼ばれた武田五一氏が洋館部分を、数寄屋大工の上坂浅次郎氏が町家部分を手がけているとのこと。当時の商家の豪華な暮らしぶりに触れられる建物です。
「麓寿庵」は2023年にオープンした町家レストラン。

明治から大正時代にかけて活躍した、日本画家・今尾景年の自宅として建てられた町家を活用しており、建物は国の有形文化財に登録されています。
人気メニューは農家直送の紀州鴨を使った鴨粥と、食べられる花「エディブル・フラワー」をあしらった華わらび。日本画家が晩年に茶の湯や盆栽を楽しんだ趣ある町家の空間で、見た目にも美しい和のメニューを楽しめます。
三条通の北側を通る姉小路通の一部も、姉小路界隈地区建築協定が結ばれ、歴史ある景観が保たれているエリアです。そのなかでもひときわ目を引く重厚な町家が、創業200年以上の老舗和菓子店「亀末廣」。

建物は創業当初の面影を残しているそうです。
亀末廣といえば、四畳半をイメージして区切られた秋田杉の箱に、千菓子を詰めた「京のよすが」が代表銘菓。ぜひ暖簾をくぐり、美しい和菓子とともに、年月を重ねた深みのある木造建築を眺めてくださいね。
子どもと一緒に楽しめる烏丸御池の博物館
烏丸御池周辺は、博物館が集まる文化的なエリアでもあります。親子でも楽しめるスポットをいくつかご紹介しますので、休日のお出かけの参考にしてくださいね。
絵本や紙芝居もある「京都国際マンガミュージアム」

日本初のマンガ博物館「京都国際マンガミュージアム」は、烏丸御池エリアでもとくに人気のスポット。30万点ものマンガ資料を手に取れるほか、マンガにまつわるさまざまな展示やイベントも行われています。
親子連れにおすすめなのが、1階の「子ども図書館」。絵本をたっぷり読めて、アンパンマンなどアニメの映像も楽しめます。
また2階で上演されている、昔懐かしい紙芝居パフォーマンス「ヤッサン一座の紙芝居」も子どもたちに人気ですよ。
建物は元小学校の校舎を活用しており、校庭が芝生の広場として残されています。

屋外スペースは持ち込みも可能なので、飲み物や軽食を持参すれば、親子でちょっとしたピクニック気分も楽しめます。
香りを体験できる「薫習館」

薫習館は、「香老舗 松栄堂」の店舗に併設された香りのミュージアム。2018年にオープンした比較的新しいスポットで、お香の文化に触れられると海外の観光客にも人気です。
お香の原料になる香木の香りを試せたり、調合を再現した展示で香りの変化を感じられたりと、体験型の展示なので親子で訪れても楽しめます。
STUDYコーナーではタブレットでお香についてより詳しく学べるので、夏休みの自由研究にもおすすめですよ。
オリジナル作品を作れる「京都万華鏡ミュージアム」

万華鏡ミュージアムは、教育施設「こども相談センター パトナ」の展示スペースを活用した万華鏡専門の博物館です。
国内外の万華鏡を400点以上所蔵しており、観てまわるだけでも楽しめますが、おすすめはオリジナルの万華鏡を作れる「万華鏡手作り体験教室」。
4名以下であれば開館時にいつでも体験できるので、ぜひ親子で万華鏡作りにチャレンジしてくださいね。
烏丸御池で人気のベーカリー
都会的なエリアで飲食店には事欠かない烏丸御池周辺には、美味しいパンが並ぶベーカリーも豊富です。
休日には、お気に入りのベーカリーで購入したパンで朝ごはんを楽しむのもいいですね。
いくつかおすすめのベーカリーをご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
ベーグルが人気の「Flip up!」

Flip up!(フリップアップ)は、行列ができる大人気のパン屋さん。2025年2月には六角通に2号店もオープンしました。写真は押小路通にある本店で、小さな店舗ですが、いつも朝からたくさんの人が訪れています。
一番人気はベーグルで、弾力のある生地で食べ応え抜群。どれを買うか迷ってしまうほど種類も豊富です。
Le Petit Mec 御池店

フランスで修行したというオーナーが展開するLe Petit Mec(ル・プチメック)は、今や東京や大阪にも出店している人気店。
京都市内にも複数の店舗がありますが、それぞれお店の雰囲気やパンの種類が異なるところが魅力です。
黒を基調としている御池店は、「黒メック」とも呼ばれシックな雰囲気。店の前にあるテラス席で、モーニングを楽しむのもおすすめです。
ランチも人気のベーカリーカフェ「Année アネ」

Année(アネ)は、京都市役所の近くで人気のCAFE KOCSI(カフェ・コチ)の姉妹店です。
レジ前のショーケースに並んだ自家製パンは、店内で食べることもテイクアウトすることもできます。
烏丸御池エリアで京文化に触れながら都会的な暮らしを
今回は京都市の中心的エリア、烏丸御池周辺の魅力やおすすめスポットをご紹介しました。
歴史ある京都の文化を残しながら、都心として発展しているこの地域では、新旧が溶け合った豊かな生活を楽しめることでしょう。
烏丸御池エリアが気になる方は、本記事でご紹介したスポットをめぐりながら、ぜひこの町の雰囲気を歩いて確かめてみてくださいね。
この地域で暮らしてみたいと思った方は、ぜひサンエーにお問い合わせください。不動産情報と建物のプランニングを同時に提案いたします。
烏丸御池エリアでのお住まい探しも、サンエーにおまかせください!
烏丸御池エリアの物件はこちら
WABI -烏丸御池-

町家風の伝統美×和モダンと暮らし
[ 120,714,000円 ]




 お問い合わせ
お問い合わせ

